第4回:中国ティードリンク業界のDX | AIが変える新商品開発・健康志向・店舗運営
中国ティードリンク業界は数万店舗規模で拡大中。 中国ティードリンクブランドは、1社で数千~数万規模の店舗を展開し、毎週のように新商品が発表されています。
技術とお茶の伝統文化、そしてユーザー体験を融合させながら、新しいサービスやビジネスを次々に生み出し、消費者のライフスタイルにすっかり溶け込んでいます。そこには欠かせない技術として「AI」が存在します。
本記事では、中国ティードリンク業界の現場で活用されているAI事例をご紹介します。
味覚・嗅覚・視覚AIが支える新商品開発
ティードリンク新商品開発において、味(味覚)・香り(嗅覚)・色(視覚)が特に重要視されています。
原材料の品質安定性やロットによる違いを判定する「差異検査」、経験豊富な専門審査員が経験を元にチェック項目ごとに感覚的に確認を行う「記述分析」、消費者が主体となって嗜好や偏向を定量化する「感情評価」など、人だけで判定していた工程に現在はAIも追加されています。
嗅覚AI : 気体の成分や匂いを定性・定量分析し、ビックデータと照合
味覚AI : 複数センサーで、酸味、甘味、苦味、渋味、塩味、うま味を数値化し、バランス分析
視覚AI : 色合い・透明度・泡の安定性・トッピングの配置などをティードリンク画像から定量化
新商品開発時には、まず人の手で製品の初步的なレシピと風味の方向性を決定し、AIを使って定量化し評価・微調整を繰り返し安定させる手法が取られています。
人の感覚を優先させながらも、AIやデジタル化を上手く取り入れ、品質管理や店舗自動化、サプライチェーン最適化へと展開しています。

サプライチェーンや自動化設備以外でのAI導入事例
※サプライチェーンの最適化や品質管理、自動化設備による店舗運営の軽減等に役立っている仕組みの紹介は以下からどうぞ。
第二回;茶葉の成長や最適な摘み取り時期、害虫予防や天気予測 に使われるAIや仕組みについて紹介
第三回:品質管理と店舗運営を軽減する自動化設備 に使われるAIや仕組みについて紹介
消費者体験の向上
VR/ARを利用した茶摘み体験を専用アプリから提供し、ブランドファンを作るとともに新しいティードリンクを通じて、お茶の伝統文化の伝承に役立てています。
注文時に利用するアプリでは注文履歴からAI自動判定されたおすすめ商品の表示や、茶百道(Cha PANDA)、益禾堂(YiHeTang)はデリバリープラットフォームと協力してアフタヌーンティーを推薦するリアルなARで販促をしています。
店舗では音声や顔スキャンを利用してすぐに注文できるなど、消費者にとって便利な機能が提供されています。
店舗運営者向けツール
茶百道(Cha PANDA)では、20前後の店舗を1人のエリア担当者が統括しており、1店舗1日の品質管理書類に添付されてくる200項目にもわたるチェック項目や400枚程度の画像確認だけでも大変な仕事量でした。これらを全てAI判定に変更したことにより、最低でも70%以上この作業の効率が上がりました。
覇王茶姫(CHAGEE)では、優良店舗の経営・運営状態が他の店舗でも参照できるようにしています。
DeepSeekなどの生成AIを利用した24時間×365日の店舗管理手帳システムは、問題解決プラットフォームとしても利用され、業務改善に有効活用されています。これは、店舗運営研修時間の大幅な削減にも役立っています。
また、このシステムは自動翻訳機能もあり、海外出店の勢いを加速させています。
AI ×養生ティードリンク | 自分だけの健康ミルクティー
中国市場では「無糖」「栄養価」「食物繊維」など健康志向が急成長。すでに市場の4割以上がお茶をベースとして、フルーツや野菜をたっぷり入れたティードリンクです。最近人気のケール入りティードリンクは、ケールの生産が間に合わなくなり、卸売り価格がこの2年で4倍となるなど、大きなブームを巻き起こしています。
フルーツや野菜の味に負けない茶葉の新品種の開発や、古代から栽培されている茶木から取れる茶葉の開発など、各ティーブランドは他社との“差別化”を図っています。
自分だけの特別な健康ミルクティー;又帰燕と鵲茶羽坊
中国語で「養生」とは、健康管理や体調を整えるという意味です。
河北省の又帰燕:AI舌診断で体質を分析し、個別処方に基づくティードリンクを提供。再購入率90%以上
南京の鵲茶羽坊:顔色・舌診断・脈診をAIで自動化し、体調に合ったドリンクを提案
健康・養生とティードリンクの組み合わせは、薬食同源(医食同源)の思想がもともとある中国の若年層にも「新しい養生体験」として注目を集めています。

4. まとめと次回予告 | 中国ティードリンク業界DXの今後 標準化とサスティナブル
DXに欠かせないAI技術が、新商品開発や原材料の品質管理といった一般的に見えない部分だけではなく、消費者体験の向上や店舗経営者の助手、さらには伝統文化を再認識させより健康を促進するトレンドを作るなど、新しいビジネスを生んでいます。
DX推進担当者にとって、単に既存業務の効率化を行うだけでなく、どのように競合優位性を確立するのか、経営者視点で考えるヒントとなるでしょう。
日本のビジネスへの応用例;
中小企業:AI導入効果を公開し、同業他社へ横展開サービスを提供
老舗や町工場、伝統工芸:伝統技術をAIに学習させ、若手教育用の自動教材を生成
飲食チェーン:AIがおすすめする健康志向メニューをSNS連動で集客
次回は、ティードリンク産業の急成長がもたらした「業界標準制定の動向」と「サステナブルへの影響」についてお話します。




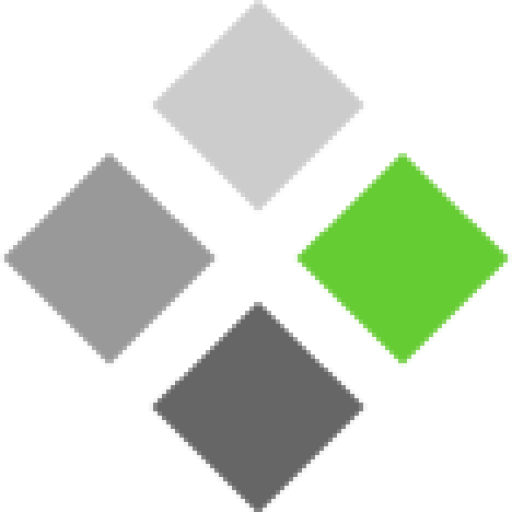






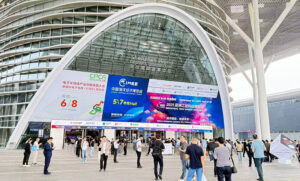
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 過や液体が触れる部分など、メンテナンスフリーのドリンク製造マシーン部品の共同開発・販売次回は、ティードリンク産業で活用されているAIと健康志向トレンドについてお話します。 […]