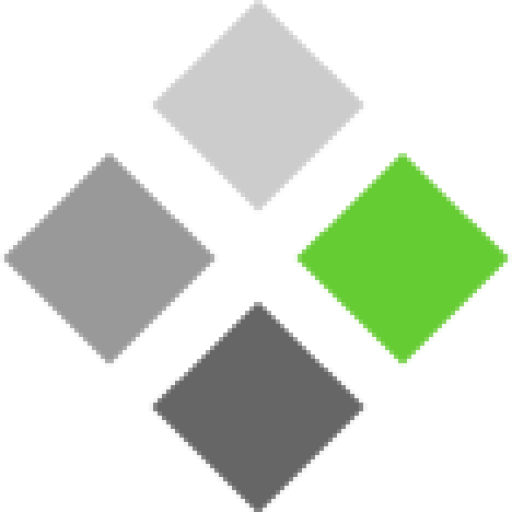中国国際工業博覧会(CIIF2025)レポート【後編】
2025年9月23-27日まで、上海国家会展中心にて中国国際工業博覧会(CIIF2025)が開催されました。1999年から始まったこの工業博は、今年第25回目となりました。
中国国際工業博覧会(CIIF2025)レポートを【前編】【後編】の2回に分けてお届けします。
【前編】では、中国国際工業博覧会(CIIF2025)の概要や、本年の展示の内容など基本的な情報を紹介しました。
本記事では、注目企業や出展の内容のレポートや、実際に中国で製造業の基礎となる金型製造工場経営をしている立場から参観して見えてきたことをお話していきます。
出展の紹介
AIという「脳」をロボットに付与して、ロボットという「体」を工場に提供することを中国では「冷起動(クールスタート)」と呼んでいます。
ハードウェアを購入して、まっさらの状態:何もわからない0歳児を急に工場で働かせるのは不可能で、導入現場での設定や動作確認、調整には莫大な時間とコストが必要でした。この問題を解決したのが微億智造です。
中国国内初! ロボット本体にAIアルゴリズムを組み込んだ企業:微億智造
微億智造は、100万件以上にもおよぶ産業シーンデータに基づくトレーニングモデルを保有しており、ロボット出荷時点ですでに「経験」を積んだ状態で出荷されます。
また、「エンド・エッジ・クラウド」の一体化管理により、ロボット本体の持つ視覚や触覚・聴覚という「感知」、AIの持つ「ディープラーニング」で次の操作を瞬時に「意思決定」し、実際の動作を「実行」する基本的な能力の提供と、経験を蓄積し知能を高める仕組み、さらに経験豊富で柔軟な人間が介入できるインターフェースを提供することで、新製造ラインの立ち上げやマイナーチェンジに伴うライン更新などにかかるコストを大幅に削減することを可能としています。
ここまでロボット本体にAIアルゴリズムを深く融合させた実例を持っているという意味で「中国国内初」ということなのでしょう。

創TRON:使えば使うほど賢くなる? 微億智造と上海捷勃特机器人(agilebot)コラボロボット
工場生産ラインにおいて、一度生産を止め違う製品の製造を開始する作業は、時間を要し、無駄が出やすい工程です。微億智造と海捷勃特机器人(agilebot)のコラボ開発ロボットである創TRONは、「多能工」を実現するロボットとソリューションで、この問題を柔軟に解決しています。
現在実際に工場で導入されている自動化ラインは、まだまだ「単一機能」の組み合わせであることが多いと思います。
創TRONは、エンボディドロボットに複数の工程プロセス能力を1台に持たせることで、一部の工程に問題が出ても数秒で他の作業でカバーするようにプログラムされています。
また、高度なスケジューリング機能と組み合わせることで、生産に遅れが生じた場合などに即座に代替え措置を取り、遅れがでている工程に多くロボットを配置するなど、安定生産を保障する仕組みを提供可能です。
昨年の工業博で初めて発表された「創TRON」は、今年、バージョンアップされた8台のロボットで4種類の製品を同時に生産する展示を行い、ロボットが単体で動き指令を待つのではなく、自分たちで考え再構築・最適化が可能な「グループ連動」ができる柔軟性をアピールしていました。本年度中に大手ヨーロッパ化粧品会社の包装ラインでの採用が決まっているとのことです。

その他、注目されていた展示
介護やヘルス関連、食品関係などのサービスロボットや、加工設備の自動化など、展示がより具体化し、理想や概念だけでなくソリューションとしてしっかりと着地させて運用していく段階に入っていることを強く感じました。
また、技術やアイデアを持つスタートアップ企業や大手企業から独立して進出など、様々な形態でロボット産業に参入しているのも特徴です。

海外企業の動向
産業用ロボットの世界4大メーカーである、ファナック(日本)、安川電機(日本)、ABB(スイス)、KUKA(ドイツ)をはじめ、減速機やサーバー機器、サーボモータ部品など、出展企業全体の約10%が海外企業だったようです。
※主催者からの正式な海外出展者の統計はまだ発表されていません。
世界4大メーカーのブースでは、大型設備など実用かつを前面に出した展示と、参観者を楽しませるエンタメ系で誰でも楽しめる展示が目立ち、ロボットをより身近に感じさせてくれます。
EPSONでは、中国市場向けの新製品発表会がありました。
研究開発、サプライチェーン、中国市場に最適化された商品など、中国企業と協力しながら進んでいくことを発表し、工業ロボットだけではなく、学校や教育機関とも連携しながらロボットを使ったソリューションを進めていくそうです。
大手企業の展示は、自社の商品展示というより業界を牽引しているトップメーカーとして、ロボット業界全体の質向上や方向性を占う展示となっていました。

中国国際工業博覧会(CIIF2025)から見えたもの
中国国際工業博覧会(CIIF2025)から見えたもの
* 「内巻」から脱出 | 融合と共生の時代へ
* エンボディドロボット&AIのプラットフォーム化
* 国産化の加速
* 価格と安全の問題 | 中小企業には遠い存在
「内巻」から脱出 | 融合と共生の時代へ
「内巻」とは、意味のない激しい競争の中で、自分や他人の努力が報われずに、成果が上がらずストレスとなっている状態のことで、ここ数年、中国社会全体に漂っていた漠然とした、何とも表現できない疲れた空気感がありました。
まだスッキリと澄み渡ったとは言えませんが、今までは「ロボット本体」を見て、わぁすごい、こんな動きがこんなに早くできる! と、表面的な戦いをしていたのが、より具体化・差別化され、新しい産業として伝統的な産業の問題を解決し、より進化するという枠に落ち着いてきた感じがあります。
ロボット業界が、単独の煌びやかで特別な世界ではなく、さまざまな産業と融合して共生していく一体感が生まれたとも言えます。
エンボディドロボット&AIのプラットフォーム化
今までのような単純で一工程を自動化する「人手の変わり」ではなく、エンボディドロボットが、「インダストリー・AIプラットフォーム」の一部に組み込まれることで、業界を横断したデータの蓄積、適応性と関連性の高い業界別のソリューションを創造、企業に新しい価値をスピーティーに提供できる仕組みが生まれています。
製造業に最適化された生成AI、仮想空間での自動学習など、今まで語られていただけで単独で動いていたものが、エンボディドロボットをという目に見えるハードウェアを介して、デジタルツインやフィジカルAIなどが、融合し実装段階に入っていることを感じました。
この先は、プラットフォーム化していかに運用していくか、今までの製造業のような上下関係ではなく、製造にかかわるすべての企業がプラットフォームの一部として共生し、必要に応じて融合を繰り返すようなオープン性がより価値を持つでしょう。
国産化の加速
ロボットは、AIという「脳」を持つことにより、より人間に近い動きを求められるようになってきました。
関節の細かな動きや、障害物を感知して回避するなどの急な動作に耐えられる「体」を実現するためには、高精度な部品が必要で数年前までは全て海外からの輸入に頼っていました。今年は、「体」のパーツが国産化され、実用に耐えうるレベルにあることが目で確認できました。
AIという「脳」も、例えば今までは5本指の動きは「5つの脳」を実装することで実現していましたが、今では腕、指、関節、足、目など全ての動きを「1つの大脳」で実現することができるようになったと、とあるメーカーの方が説明してくれました。
海外製の部品が、単独で「高技術」を誇示伝達するのではなく、中国もしくはロボット業界という大きなシステムの中に融合されることでより市場が拡大し、技術の進歩が加速するということなのかと考えます。EPSONの新製品発表からもこの流れが見て取れます。技術の全世界化とローカライズの融合を高度に実現できるのが、中国であるというアピール力は絶大でした。
価格と安全の問題 | 中小企業には遠い存在
ロボットを「設備投資」と考えると、その投資がいつ回収できるかという視点(ROI)が重要になります。
ロボットの量産化が進み、買える価格になってきた印象があるものの、特に中小企業は小ロット多品種生産や複雑な工程を担っていることが多く、エンボディドロボット+AIはまだまだ「大企業向け」である感が否めません。
また、操作安全性の確保やハードウェア・ソフトウェア更新などの保守・運用を中小企業単体で担うには人的・コスト的にもまだまだ負担が大きく、クラウド利用の場合でもネットセキュリティ対策が必要となり、そこまで踏み込めている展示はほぼありませんでした。
ロボット自体が身近な存在になりつつありながら、中小企業の導入という点においてはまだまだ遠い存在と言えると思います。

まとめ
中国国際工業博覧会(CIIF2025)のレポートをお伝えしました。
中国国際工業博覧会は、西の産業見本市「HANNOVER MESSE」(ドイツ開催)と並んで、製造業(工業)の動向を探る重要な展示会であり、特にロボット分野は技術・AI・市場など、さまざまな面から優位を持っていることがわかりました。
* エンボディドロボットとAI融合、プラットフォーム化で共生
* スタートアップ企業が続々成果を出し、「内巻」脱却
* 海外依存から国産化への移行
* 海外企業は中国市場と「融合」し、中国企業と一緒に「拡大」
ロボット産業は今後、自動車産業と並ぶ大きな産業に成長すると考えており、注目しています。
来年の本工業博はもちろんのこと、2026年5月14-16日に浙江省・杭州で行われる「杭州国际人形机器人与机器人技术展览会」へも参加することが決定しました。
ご興味がある方は、問い合わせフォームよりご連絡ください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事から何かしらのヒントや情報を得てくださり、少しでもお役に立てたなら幸いです。
本ブログは、実際に中国で製造業の基礎となる金型製造工場経営をしている立場から、中国メディアのニュースなどを元に現場でのリアルな状況を加えて、独自にお伝えしています。
今後も、中国情報をアップデートし、中国の事例から日本の中小企業が学べる未来のヒントを発信していきます。