第3回:DXで進化した茶葉加工技術とドリンク製造機
中国のティードリンク業界は、なぜ多彩な商品を数千・数万規模の店舗で同じクオリティでスピード提供できるのでしょうか。
その答えは、茶葉加工技術や各店舗で導入されているドリンク製造機も進化を続けているから。茶葉研究機関や専門家による研究開発と、市場をよく知るティードリンクブランドが一体となってティードリンク業界全体のクオリティを高めているのです。
本記事では、「多種多彩なハイクオリティ・ティードリンクのスピード提供」を裏で支える、お茶抽出や茶葉加工の技術とドリンク製造機を通じて進められている、中国式DXを紹介します。
「お茶抽出」を科学する産学協力体制
ティードリンクの味を左右するのは、やはり“茶葉”とその茶葉が本来持つパワーを最大限に引き出す技術。本来の風味をできる限り引き出し、栄養価を維持するために、それぞれの茶葉にあった抽出方法をティードリンクブランド主導のもと、茶葉加工設備会社茶葉研究機関の専門家などが産学協力体制で研究しています。
細胞レベルの茶葉粉砕技術と超臨界流体技術
一般的に常温以下(20度以下)で、低温抽出や冷間抽出とも呼ばれています。茶葉中のカテキン、アルカロイド、フラボニジンなどに代表される苦味成分は、低温条件下ではその流出が抑えられるため、さわやかな味を表現したい時に採用されていました。しかしこの抽出方法は、専用の抽出設備が必要となり抽出に時間がかかってしまう点や、栄養成分が抽出されにくく、茶葉の持つ甘味も出にくいことが欠点でした。
研究を重ね、茶葉自体を超音波、マイクロ波などの技術で細胞レベルで粉砕することで、苦みを出すことなく栄養価を保ったまま、短時間で抽出することに成功。また、超臨界流体技術を利用した抽出も進んでおり、茶葉から苦み成分や香り、栄養価を分離し、「香り・色・栄養価」等を調整して、より消費者の嗜好にあったティードリンクのベースを作り上げています。
セグメント式抽出技術
伝統的な中国茶を淹れる茶器:蓋椀(蓋付きの茶碗)、茶壷(急須)、茶海(ピッチャー)、聞香杯(残り香を楽しむための専用の器)などには、それぞれ茶を味わうための、伝統的な役割があります。
今まで人の手で管理されていたこれらの技術を、ビックデータとして集約。茶器の役割と、茶葉ごとの特徴を自動判別し、お湯の温度や抽出時間をコントロールするなど、お茶を淹れる各工程をセグメント化して自動抽出します。
「伝統の標準化」により、味がブレることがなく、表現したい味をすぐに抽出できるようになったことで、新商品開発をより加速することを可能としました。

茶葉加工の革新
中国茶葉流通協会の発表によると、2024年ティードリンク業界で使われた茶葉総量は約30万トンで、中国国内で消費された茶葉の12%に相当します。
各ティードリンクブランド直営の茶畑だけでは足りないため、様々な地域の茶畑と提携して仕入れる必要があります。
第2回:人気ティードリンクを支える、サプライチェーンのスマート化で紹介したように、5GやIoT技術を利用したスマート茶農園を実現しているものの、産地が変われば同じウーロン茶でも、風味が異なります。
同じように、ジャスミンティーやフルーツティーなど、茶葉に香りを添加する際にも少なからず違いが生じるものです。
各地で生産された茶葉をデータ化し、それぞれの産地にあった遠赤外線焙煎技術で紅茶の香ばしさを引き出したり、ウーロン茶を90度・80度・70度の三段階焙煎技術で甘みを増加させカフェインや変色成分を減少させることで、より茶葉本来が持つ芳醇な香りを引き出します。
また、最近の「0添加物」嗜好に合わせて、茶葉乾燥時に、ドライフルーツや花を一緒に入れてより茶葉の香りを際立たせ果物や花の香りを長持ちさせる花果混合賦香と呼ばれる技術も進化してきており、果汁等を絞るだけでなく、蒸気や発酵を応用した技術も採用されています。
地道な研究の積み重ねとデータの蓄積と様々な加工技術の自動化により、一定の品質に保たれた産地の違う茶葉でも、加工工程で同じ品質に仕上がる仕組みがあります。
ドリンク製造マシーンの最前線
デジタル化や技術の進化を受け、各ティードリンクブランドは各店舗で実際に使うドリンク製造マシーンの開発も加速させています。
覇王茶姫(CHAGEE)は、圧力フラッシュ抽出技術で濃縮茶を抽出し、その後ミルクやフレッシュ果汁などとブレンドするだけの設備を開発しました。その後も店舗でのオペレーションをできるだけ減らす設備を積極的に開発し、製造マシーンに水を入れることと、最後に蓋をするだけという簡単操作を目指しています。
喜茶(HEYTEA)は、2024年4月に中国で開催された展示会で独自開発の製造マシーンを発表しました。
茶葉の鮮度を製造日から起算し、原料特徴に基づいた適正温度で貯蔵する機能、自動計量、茶葉種類ごとの自動抽出機能などをコンパクトにまとめ、各店舗でのお茶の管理を簡単にすることで、人的ミスを減らし品質向上・コスト削減を達成できるようにしました。
その他、果物の搾汁機に自動皮むき・種取り機能なども開発し、店舗オペレーションの負担を軽減しています。

奈雪的茶(Naisnow)が開発したスマートドリンク製造マシーンは、ティードリンクレシピが記憶されています。
レシピにより最短6秒で1杯が出来上がるように設計されていて、消費者の待ち時間大幅削減とオペレーションの簡素化を同時に実現し、計算上店舗管理コストを40%程度削減できると言われています。
ドリンク製造マシーンを開発しスマート化することで、統一された品質を保証しながら、フランチャイズ参加や直営店の店舗管理費用の負担を減少。店舗運営側はドリンク製造マシーン等の初期導入費用がかかっても、回収サイクルが早いので加盟希望者は増加、ティードリンクブランド側にとっても容易に店舗数拡大を実現できる好サイクルを生み出しています。
まとめと次回予告 | 味覚を科学するAIと健康志向トレンド
「この秋1杯目のミルクティー」を通じて、市場をよく知るティードリンクブランドが、茶葉研究機関や専門家などと一体となってデジタル化やスマート化を推進することで、ドリンク業界全体のグレードアップに大きな影響を与えています。
DXが目的化せず、手段の一部として有効活用されているのです。
関連する技術を持った日本の中小企業で、自社の強みを生かした商品での市場参入の検討をしたり、研究開発部分を大学や関連研究機関など専門家との連携で新商品発売を加速させたい現場などで、DX推進するヒントになるでしょう。
日本のビジネスへの応用例;
超微粒粉砕特許技術を、冷凍保存茶葉やドライフルーツを丸ごと粉砕するビックデータと合わせて付加価値販売
濾過や液体が触れる部分など、メンテナンスフリーのドリンク製造マシーン部品の共同開発・販売
次回は、ティードリンク産業で活用されているAIと健康志向トレンドについてお話します。




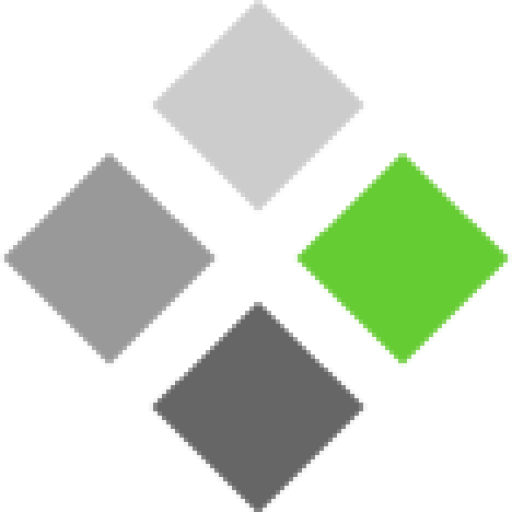






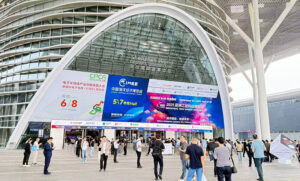
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 【連載】この秋1杯目のミルクティー | サプライチェーンDXとカルチャーの交差点 […]